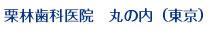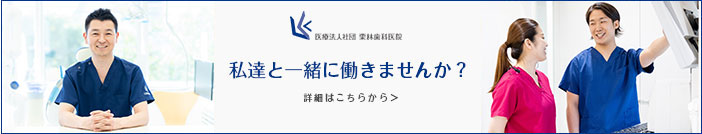暖かくなってくると気をつけないといけないのは、食中毒です!
食中毒菌であるカンピロバクター、黄色ブドウ球菌、ウェルシュ菌の原因・対策について紹介します!
カンピロバクター
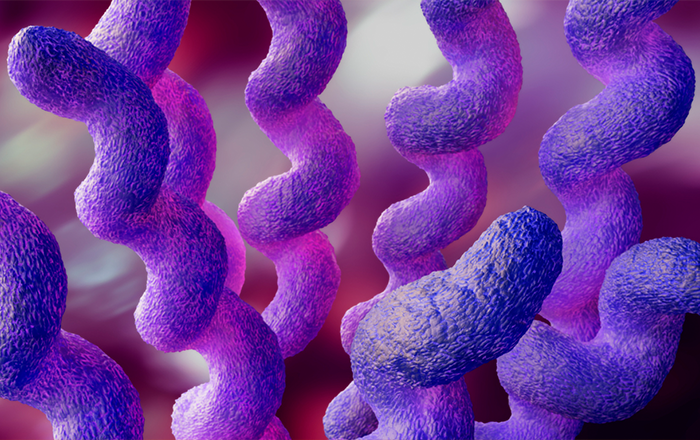
カンピロバクターは動物の腸管に存在し、乾燥や熱に弱い菌です。
十分に火が通っていないお肉(主に鶏肉)、生野菜、飲料水などが原因となります。
食後2-7日後に下痢や発熱等の症状が起こります。
また、稀にギランバレー症候群という
麻痺や呼吸困難などの重篤な症状が出る場合があるため、注意が必要です。
対策としては、熱に弱い菌であるため中心部まで十分に加熱することが大切です。
調理中は生の状態のものを触るため、専用のトングや橋を使い、食事用とは分けるようにしましょう。
黄色ブドウ球菌

黄色ブドウ球菌はヒトの皮膚や鼻・口腔内に存在する菌です。
そのため、傷やニキビなどに触れた手で食べ物を触ると菌がつきやすくなります。
おにぎりやお弁当、お寿司、惣菜パンなど素手で触る食品が原因となることが多いです。
食後30分-6時間後に吐き気や腹痛などの症状が現れます。
対策としては、食品を素手で触れないようにするためラップや使い捨て手袋を使用しましょう。
熱に強く、加熱しても防ぐことができないため、気をつけてください。
ウェルシュ菌
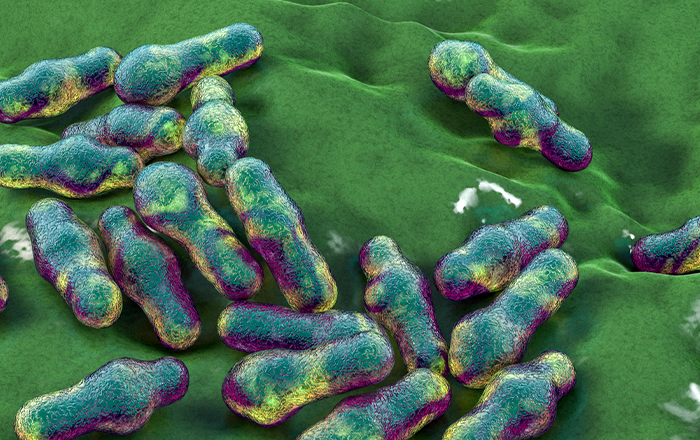
ウェルシュ菌は酸素がない場所で増殖する菌で、特に牛・鶏・魚が保菌していることが多いです。
カレーやスープなどの煮込み料理が原因となります。
食後6-18時間後に水溶性の下痢や軽い腹痛などの症状が現れます。
酸素の少ない鍋底近くが危険です。対策としては、調理中は鍋底までしっかりかき混ぜること、室温で放置せず、保管する時はすぐ冷蔵庫に保管するようにしましょう。
食中毒を予防するために、3原則を意識するようにしましょう。
①つけない
②ふやさない
③やっつける
これらを守ることで、食中毒から体を守ることができる可能性が高まります。
梅雨だけではなく、どんな季節でも食中毒に注意して過ごしましょう!
参考文献
・「子どもの食育 注目しよう!食べ物のこと 食中毒予防」農林水産省